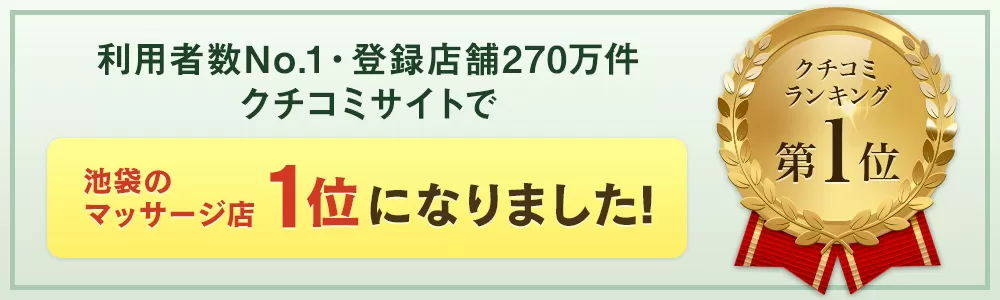
Campaign
期間限定キャンペーン
※詳細はバナーをクリックして確認して下さい
SSC movie
SSC紹介動画
Concept
SSCマッサージの想い

「心身ともに癒す」が当店のモットーです。

「手当て」という言葉があります。
この言葉は、文字通り、まだ医学があまりすすんでいなかった時代の人々が病気や怪我で苦しんでいる人を前になすすべを知らず、それでもなんとか楽にしてあげたいという思いから、その痛むところに手を当てたことから、現在の意味として使われるようになったと言われています。
自分が学んだ上海中医薬大学の気功研究所でも、「気功を施す上で一番大切なことは相手に対する真実の思いやりと誠実さであり、これが最大の効果をもたらす」と教えられました。
私たちがお客様に接するときに一番大切にしていることは、まさにこの「相手に対する真実の思いやりと誠実さ」です。
「お客様からいただいた時間の中でできるだけ楽になっていただきたい、身体だけでなく心まで癒したい」という思いを全員が持っています。
また、「きちんとした接客の作法を身につけているのか?」と言われれば恥ずかしいかぎりですが、私たちなりに一生懸命誠意をもってお客様に接しているつもりです。
当店にお越しいただければ、よそのマッサージ店にはない「心身ともに癒される」を御実感いただけると思います。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
スタッフ一同
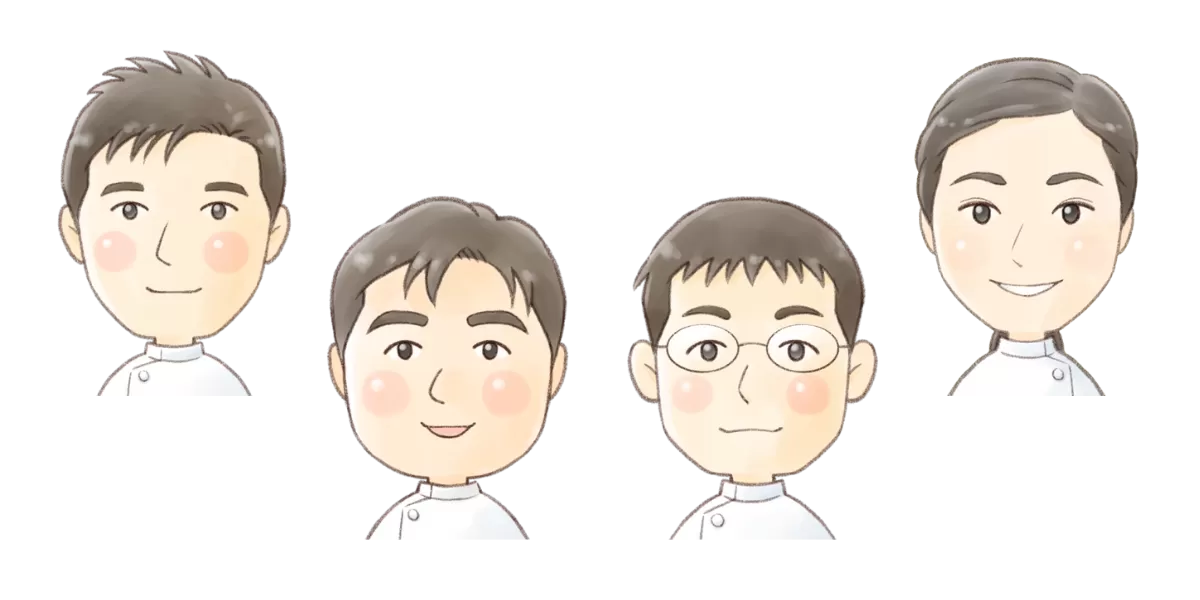
Choose
選ばれる理由
-

池袋に3店舗30年の信頼と実績!
-

心身ともに癒やします!
-

ベテランスタッフによる本格施術
Reserve
施術の予約
Choice
おすすめ
Voice
お客様の声
-

M.K 様
池袋で一番のマッサージ店だと思っています。本当に身体も心も癒されています。色々な所に通っておりましたが、ここが一番です。事務仕事と不規則な生活のため、肩こりや腰痛がひどく、職場のある銀座や乗り換えの池袋ではかなりのお店に行っていますが、技術もサービスもこちらがズバ抜けて気に入っています。
-

S.M 様
3年くらい通っています。かれこれ3年くらい通っています。競技スポーツをしていて、通いつけのマッサージ予約が取れず、とりあえずで予約してみました。リラクゼーションぽい雰囲気なので、正直期待はしていませんでしたが、その日から3年ほど通い続けています。昔からマッサージ慣れしていて、様々なお店を経験しましたが、筋肉をしっかりほぐしてもらえるのでとても楽になります。スポーツしている方にもとてもおすすめです!☆
-

K.H 様
大当たり!駅から近いところで探していたら、西口の目の前なので言ってみたら大当たりでした。最初のカウンセリングもすごく丁寧で最初からこれは期待できるという雰囲気でしたので安心してマッサージされることができました。技術はもちろんですが、術後の説明もわかりやすく丁寧で絶対にまた行きたいと思いました。
Other
その他
Shop
店舗情報
Blog
ブログ
- 健康コラム
腸活を実践!!便通改善で免疫力を高めよう!
2024.04.19腸活をするメリットは、便通を改善へと導いてくれることです。 腸活を実践することで、下痢や便秘が気にならなくなれるでしょう。 効果がみられるようにするためには、まず食生活や生活習慣を整えて...
- 健康コラム
腸の働きを良くする3つのツボをご紹介!!
2024.04.03腸の働きが悪くなると、便が出にくくなりお腹に張りを感じるなどの不快感が現れてきます。 2~3日排便がないと、お腹が痛くなることもあるでしょう。 忙しい毎日を過ごしていても、毎日快便であることが健康的で...
- 健康コラム
免疫力を高める4つの方法を簡単解説!!
2024.02.29免疫力を高めると、体調を悪くしにくい 悪くなったとしても、回復が早い 疲れにくくなるなどの効果があります。 免疫力を高めるようにしていると、毎日元気に過ごすことができます。 今回は、免疫...


















